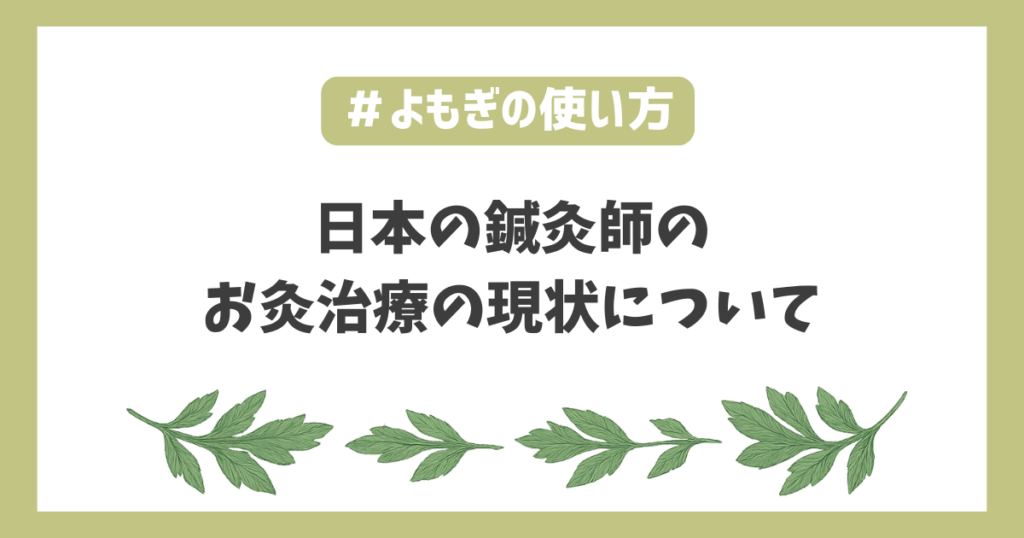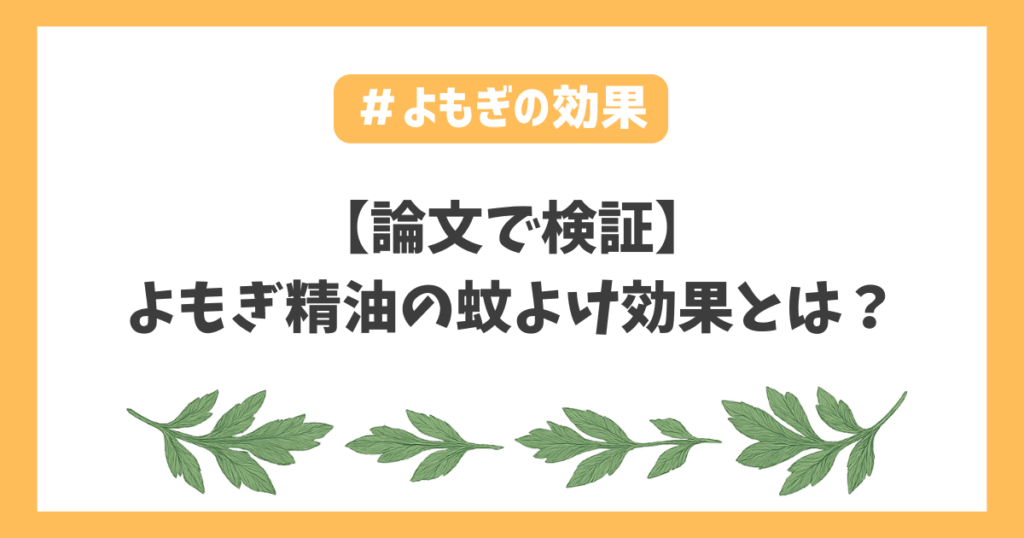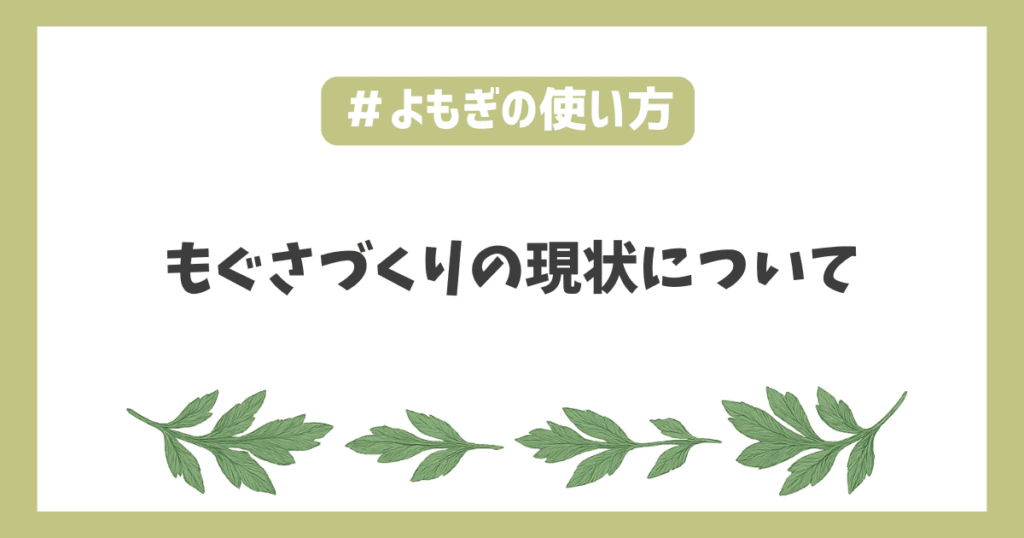こんにちは。
今回はお灸の現状についてお伝えしていこうと思います。かなりリアルな内容ですがぜひ知ってもらいたい内容です。
この記事では、日本で今、お灸がどう使われているのか、
そしてどんな課題があるのかを、1,500人以上の鍼灸師のアンケートの論文をご紹介します。
「お灸って最近どうなの?」「本当に使われてるの?」
そんな素朴な疑問に、現場のリアルな声でお応えできる内容かなと思います。
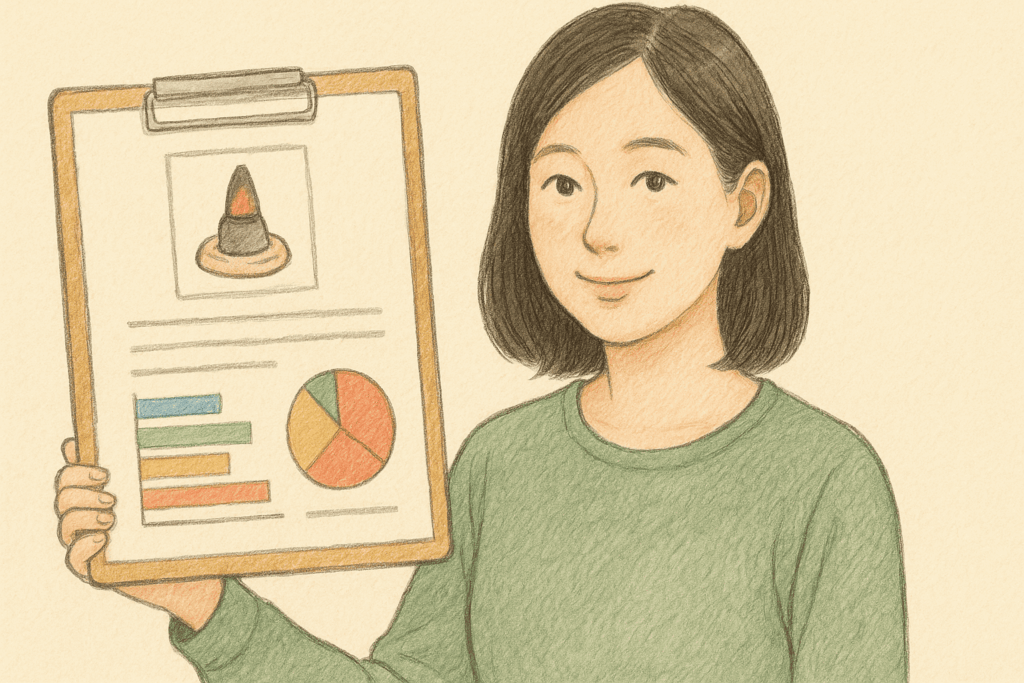
目次
- なぜいま、“お灸の実態調査”?
- 現場で実際に行われているお灸
- お灸を受けたがらない理由とは?
- 事故(インシデント)は起きているの?
- それでも「お灸には効果がある」と、98.9%が回答
- これから広げていくためには?
- おわりに:お灸は、“これから”のヘルスケアにもフィットする
なぜいま、“お灸の実態調査”?
かつては、鍼とお灸は同じくらい大切に使われていました。
でも1980年代からは「鍼のほうが中心」になり、教育現場でもお灸の存在感は少しずつ薄れていきました。
それって本当に今の現場でも同じなの?
そもそも、患者さんはお灸をどう感じているの?
そういった疑問に答えるために、全国の国家資格を持つきゅう師を対象に、2022年に大規模なアンケートが行われました。
- 調査期間:2022年1月25日〜2月24日
- 方法:Googleフォームでの無記名アンケート
- 回答数:1,507名(全国全都道府県から)
- 実施:筑波技術大学(倫理審査済)
現場で実際に行われているお灸
なんと、95.1%の鍼灸師が臨床でお灸を使っているという結果に!
「お灸ってもう使われてないんじゃ…?」という印象とは大きく異なりますよね。
ただし、施術の主軸はやはり鍼。
- 「お灸より鍼が多い」→52.9%
- 「半々」→36.1%
よく使われているお灸の種類は?
- 知熱灸:66.3%
- 透熱灸:53.4%
- 台座灸:79.5%
- 棒灸:49.8%
最近では電子灸や電気灸など“火を使わないお灸”も30%以上の治療家が活用しており、
スモークレス灸具も37%が使用中。
煙や火を気にする人にも配慮したやさしい選択が広がっています。
お灸を受けたがらない理由とは?
ここが一番大切なポイントです。
実は、患者さんからお灸を断られたことがあるという鍼灸師は…なんと45.6%もいました。
その理由として多かったのは:
- 「熱そうで怖い」
- 「火傷しそうで心配」
- 「跡が残るのがイヤ」
- 「煙やにおいが気になる」
こうした声が、お灸から足を遠ざけてしまう原因になっています。
でも、実際の“香り”評価は…?
- 「心地よい」→62.9%
- 「どちらでもない」→43.3%
つまり、不快と感じている人は実は少数派。
とはいえ、煙の安全性を「安全」と答えたのは30.1%のみ。
「わからない」「どちらとも言えない」が半数以上という結果からも、治療者側もまだ確信を持てていない部分があるようです。
事故(インシデント)は起きているの?
残念ながら、52.9%の鍼灸師が何らかのインシデント経験ありと回答。
- 火傷(61.9%)
- 水疱(55.3%)
- 備品の焦げ・焼損(61.8%)
特に台座灸や透熱灸での発生が多く、「間接灸でも油断は禁物」ということが分かります。
中には賠償責任保険を使ったケースも4.0%、自己資金で補償したケースが5.0%と、現実的な課題にもなっているんですね。
それでも「お灸には効果がある」と、98.9%が回答
圧倒的多数の鍼灸師が、お灸にしっかり効果を感じていると答えています。
よく使われている症状は、
- 腰痛
- 膝痛
- 肩こり
- 冷え性
といった運動器系や冷えにまつわるものが中心。
また、「病名だけでなく東洋医学的な“体質や流れ”を考えて施術している」という声も多くありました。
これから広げていくためには?
治療家たちの87.5%が「もっとお灸を普及させたい」と考えていることも分かりました。
そのために必要とされているのが:
- 臨床研究で有効性を示すこと(75.6%)
- 科学的な裏づけを増やすこと(68.3%)
- わかりやすい啓蒙活動(63.9%)
- より安全な灸具の開発(34.2%)
つまり、「安全に・科学的に・わかりやすく」伝えていくことが今後のお灸のカギになりそうです。
おわりに:お灸は、“これから”のヘルスケアにもフィットする
ここまで読んでくださってありがとうございます。
お灸は、長い歴史をもつ伝統療法ですが、
いま改めて注目されている理由は、その手軽さ・温かさ・自然なケアにあります。
「熱そう」「煙がちょっと…」と感じていた方も、
スモークレス・低温灸・電子灸など選択肢が広がることで、もっと気軽に体験できるようになってきています。
鍼灸師の現場では、お灸は“今もちゃんと使われている”し、“これからも続けたい”と強く思われている。
それを今回の調査は、数字とともに教えてくれました。
ぜひ一度、あなたも“自分に合ったお灸”を見つけてみてくださいね。
\「お灸ってちょっと気になる…」という方は、ぜひ身近な鍼灸院に相談してみてください!
参考文献:日本における灸療法 形井ら 全日本鍼灸学会雑誌,2025年
また弊社ではよもぎ商品の販売を行っております。
ぜひご購入ください!
SHOPはこちらから