こんにちは
YOMOGI BASEの矢澤です。
「よもぎって草餅のイメージしかない…」そんな方も多いかもしれません。ところが近年の研究で、よもぎの効果の中でも“抗酸化作用”がひときわ注目を浴びています。この記事では論文データをもとに、
- 抗酸化とはそもそも何か
- よもぎにはどんな抗酸化物質が含まれるのか
- 実験でわかってきた健康への可能性
を、専門用語をできるだけ噛み砕きながら解説します。
読み終えた頃には「よもぎを生活に取り入れてみようかな?」と思うかも
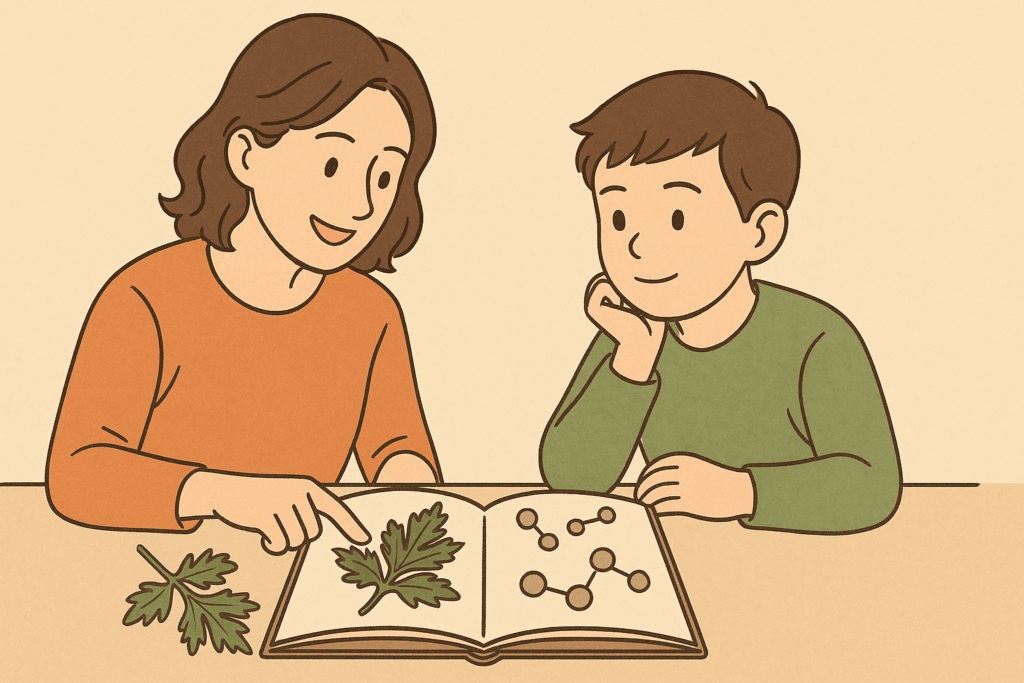
目次
- 1. 抗酸化って何? まずはサビ取りのイメージから
- 2. よもぎに含まれる主な抗酸化物質
- 3. 実験でわかった! よもぎの抗酸化パワー
- 4. 抗酸化だけじゃない! よもぎの多彩なヘルスサポート
- まとめ──“飲むサビ取り”を毎日の習慣に
1. 抗酸化って何? まずはサビ取りのイメージから
私たちの体は呼吸で取り込んだ酸素をエネルギーに変える一方で、活性酸素という“サビ”を生むことがあります。
活性酸素が増え過ぎると細胞を傷つけ、老化や生活習慣病のリスクを高める――これが酸化ストレスです。
体内にはビタミンCやグルタチオンペルオキシダーゼなど“サビ取り酵素&物質”が備わっていますが、現代のストレスや食生活で追いつかない場合も。そこで食事やハーブで外から抗酸化物質を補うことが注目されています。
2. よもぎに含まれる主な抗酸化物質
研究で確認されている代表的な成分を、分かりやすく三つに分類します。
| グループ | 主な成分例 | ひとことポイント |
|---|---|---|
| 精油 | 1,8‑cineol/α‑pinene/camphor など | 香り成分。リラックス効果も期待 |
| フラボノイド | クエルセチン誘導体/ジャセオシジン ほか | 植物由来ポリフェノールの王道 |
| ポリフェノール | クロロゲン酸/カフェタンニン類 | コーヒーにも多い成分で強力なラジカル捕捉能 |
豆知識
日本産よもぎの総ポリフェノール量は4.6 %前後という報告があり、ジャスミン茶やウーロン茶に匹敵します。ハーブティーとしてはかなり優秀とのことです。
3. 実験でわかった! よもぎの抗酸化パワー
3‑1. 試験管レベル(in vitro)
- DPPHラジカル消去試験:濃度依存的にフリーラジカルが減少
- 脂質過酸化抑制:細胞膜モデルで“サビ”生成をブロック
- タンパク質断片化の抑制:酸化で切断されるタンパク質を守る
- ONOO⁻スカベンジング:強力な酸化物質ペルオキシナイトライトも除去
- ジャセオシジンの働き:悪玉LDL酸化を抑え、炎症伝達NF‑κBをブレーキ
3‑2. 動物レベル(in vivo)
肝障害モデルラットによもぎエキスを投与すると…
| 指標 | 効果 |
|---|---|
| GOT・GPT | ダメージ指標が低下=肝細胞保護 |
| SOD | サビ取り酵素が増加 |
| GSH | グルタチオン増加で抗酸化防御UP |
| MDA | 脂質過酸化産物が減少 |
まとめると
よもぎは“サビを取る”だけでなく、“サビに強い体をつくる”ダブルの働きが示唆されています。
in vitro(イン・ビトロ):体の外、試験管やシャーレで“成分の動き”だけを観察する実験。
in vivo(イン・ビボ):体の中、動物や人で“本当に効くか”を確かめる実験。
ふつうは「外でざっくり確認 → 良さそうなら体内で再チェック」という順で進みます。
4. 抗酸化だけじゃない! よもぎの多彩なヘルスサポート
- 血糖コントロール
- フラボンの一種エウパチリンがインスリン分泌をサポート
- 筋細胞でGLUT4(糖取り込み口)を増やす可能性
- 免疫バランス調整
- 炎症性T細胞を抑え、制御性T細胞を活性化
- アレルギー反応のキー物質IgEを低減(マウス試験)
- がん細胞へのアプローチ
- ヒト乳がん細胞MCF‑7でアポトーシス(細胞死)誘導
- Hela細胞でも同様の報告
「抗酸化=若々しさ」だけでなく、よもぎの効果が全身で期待できる理由が少し見えてきます
妊娠中・授乳中、キク科アレルギーの方は医師に相談を。
まとめ──“飲むサビ取り”を毎日の習慣に
- 活性酸素を抑えることは、エイジングケアや生活習慣病予防に直結
- よもぎには精油・フラボノイド・ポリフェノールなど多彩な抗酸化物質
- 試験管・動物試験で“サビ取り”&“防錆コート”の二重効果を示唆
- 血糖・免疫・美容面でもプラスが期待される
今日のアクション
まずは一杯のよもぎティーから、抗酸化生活を体験してみませんか?
●参考文献
商品のご購入はこちらから
⏩️ 公式ショップ

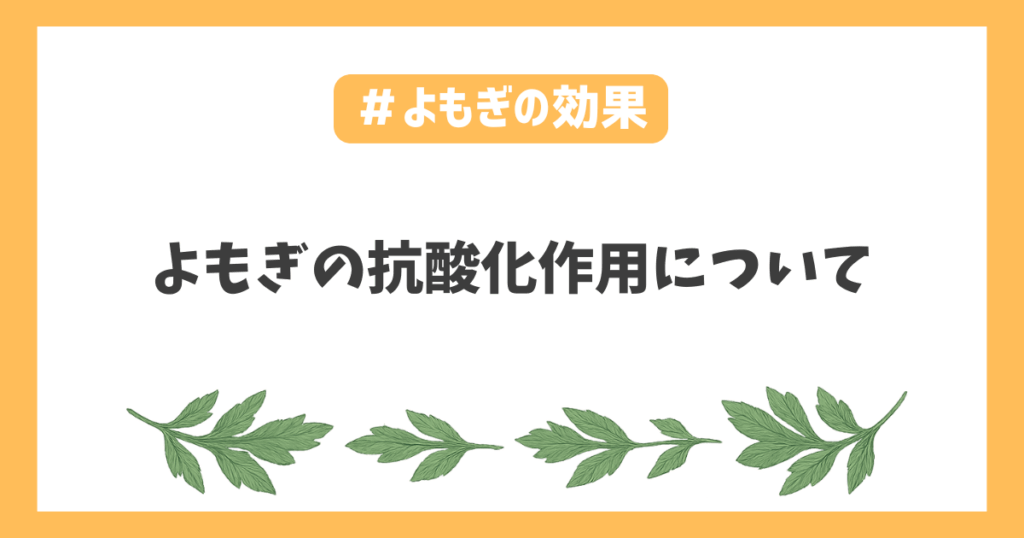
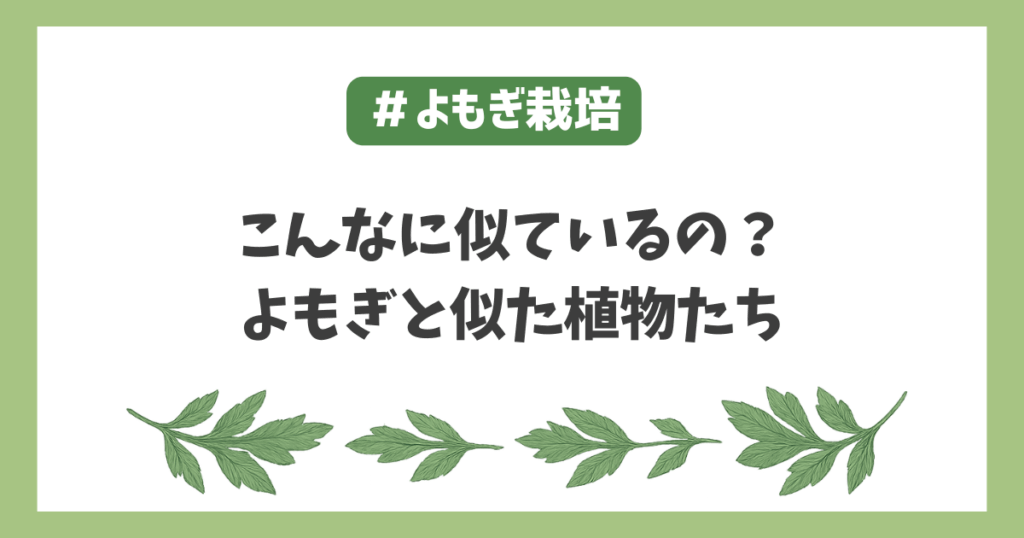

ピンバック: 🍃よもぎパウダーで淹れる、よもぎティーのいちばんおいしい飲み方3選 - yomogi-base